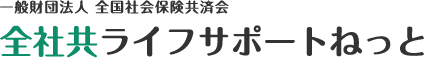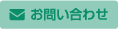亡くなったとき、家族に遺される年金
私たちが「年金」と聞いてまず思い浮かべるのは、自分自身の老後の生活を支える手段としての老齢年金のことでしょう。日本に住む人はすべて、20歳から公的年金に加入することになっており、①加入制度が国民年金(自営業者やフリーランスの人など)だけの人には「老齢基礎年金」が、また、②厚生年金保険(会社員や公務員など)に加入したことがある人には「老齢基礎年金」と、それに上乗せして「老齢厚生年金」が支給されます。
公的年金にはさらに、けがや病気で障害が残ったときや、生計を支えていた人が家族を遺して亡くなったときに支給される年金があります。それが、障害年金と遺族年金です(老齢年金と同様に、それぞれに基礎年金と厚生年金があります)。
「終活」を考える年齢になった方にとって気になるのは、自分が亡くなった後に家族に何を遺せるのかということ。ここでは、終活世代の方が亡くなったとき、遺された家族に支給される年金にはどのようなものがあるのかを見てみましょう。
まだ支給されていない老齢年金があるかもしれない
すでに老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらっている場合を考えてみましょう。年金を受給している本人が亡くなると、年金の支給は終了します。しかし、本来、受け取れるはずだった年金が、亡くなった時点でまだ支給されていないことがあるかもしれません(未支給年金)。この場合、支給されていない年金は「遺族」に支払われることになります。
公的年金は年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われることになっており、このときに支払われる年金は支払月の前2ヵ月分が後払いとなっています。たとえば、6月に支給される年金は、4月と5月の2ヵ月分。つまり、5月に亡くなった場合は、4月分と5月分が支払われていないことになります。
未支給年金を請求できる「遺族」は、死亡した受給者と生計を同じくしていた(同居、仕送りなど)①配偶者(夫・妻/以下同様)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、他の三親等以内の親族です。ここに列挙した順番に順位が決められており、先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。同一順位の遺族が複数いる場合は、代表で1名が請求します。手続きは、最寄りの年金事務所で行います。
なお、年金を受ける権利は受給者に固有のもので、親族であっても他人に譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。未支給の年金は、一定の要件に基づいて給付として遺族に支払われるものであり、相続財産として支払われるものではありません。したがって、要件を満たす親族がいない場合は、遺言書で相続人が設定されていても支払われません(ただし、すでに支払われた年金は、財産として相続の対象になります)。
遺された家族に支給される遺族年金
公的年金には、自らの老後を支えるための老齢年金のほかに、遺された家族の生活を支える給付があります。年金に加入している(加入していた)人、老齢年金を受けている人が亡くなったときに、一定の要件を満たしていれば、生計をともにしていた家族が遺族年金などを受けることができます(下表参照)。

「終活」を考え始めた世代では、子どもがいても条件となっている年齢を超えていることが多く、「遺族基礎年金」を受けられるケースは少ないでしょうが、上の表の「そのほかの遺族」欄の給付対象となる可能性があります。この場合、遺族は、亡くなった人が国民年金だけに加入していたときは「寡婦年金」または「死亡一時金」を、厚生年金保険に加入していたときは「遺族厚生年金」を受けることができます。
受給できる遺族とは?
遺族年金を受けられる「遺族」を整理してみます。
遺族基礎年金を受けられる遺族
遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
(1) 死亡した人の配偶者であって、子と生計を同一にしている人
(2) 死亡した人の子
ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは支給停止されます。
なお、子は、死亡した人の死亡時に18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子か、または20歳未満で1・2級の障害のある子に限られます。
遺族厚生年金を受けられる遺族
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
(1) 配偶者(妻には年齢制限はないが、夫は55歳以上であること)
(2) 子(18歳到達年度の末日まであるか、20歳未満で1・2級の障害のあること)
(3) 父母(55歳以上であること)
(4) 孫(18歳到達年度の末日まであるか、20歳未満で1・2級の障害のあること)
(5) 祖父母(55歳以上であること)
遺族厚生年金を受けられる遺族の順位も、この順番で決められており、先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。また、死亡した人の死亡時に55歳以上であることが必要である夫、父母、祖父母については、支給開始は60歳からとなります。
寡婦年金・死亡一時金が受けられる遺族
「寡婦年金」は妻が対象で(夫は対象外)、婚姻関係(内縁関係の場合も含む)が10年以上継続しており、夫の死亡当時に生計維持関係があった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。また、「死亡一時金」は、死亡した人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、他の三親等以内の親族です。
遺族への給付では、「生計をともにしていたこと」が重要なポイントです。死亡時に遺族が、死亡した人によって生計を維持されていたことが求められており、具体的には、生計が同一で、遺族の年収が850万円以下であることが必要です(死亡した本人の年収は要件になりません)。