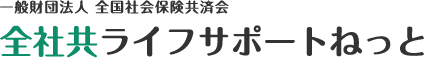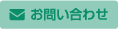相続は家族の「争いの種」になることも
「終活」を始めるにあたって気になることは、残される家族に苦労をかけたくないということ。特に相続の問題は、「争族」(家族の間での争い)に発展することも多く、トラブルの種は、できるだけ早いうちから摘み取っておきたいものです。
「自分には財産がないから、相続の問題は生じない」と考える方も多いでしょうが、額が大きいほどしっかり準備がなされ、問題は起きにくくなるもの。何も備えがなければ、かえって問題は生じやすくなるのです。たとえば、遺産分割事件(認容・調停成立)で争われた遺産の額は、1,000万円以下が3分の1を占め、5,000万円以下になると8割近くを占めます(「司法統計(家事事件編)」平成30年度)。
まずは、相続とはどのようなものなのかを知り、具体的に、残された家族の誰が、どのような問題に直面することになるのかを考えてみることが大切です。では、相続の基本をご紹介します。
相続できるのは誰?
相続とは、亡くなった人の財産を、特定の人が譲り受けることをいいます。財産を譲る人(亡くなった人)を「被相続人」、財産を譲り受ける人を「相続人」といいます。相続には、①被相続人が遺言書で相続人を指定する場合と、②遺言書がなく、法律で定められている相続人(法定相続人)が相続する場合の2パターンがあります。
①の場合、亡くなった人が、遺言書によって誰に何を譲るかを指定します。具体的に誰に何を譲るかを指定したり(「Aには○○の土地、Bには××の有価証券」など)、譲る財産の割合を指定することも可能です(「Aには財産の1/3、Bには1/4」など)。
②の場合はどうでしょう。この場合、相続人として一定の親族が民法で定められており、相続の優先順位や相続割合も決まっています(表1)。

※ 子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合、同順位者間で均等に按分します。順位が上の人がいる場合、それより下位の人は法定相続人になれません。
ただ、①の場合であっても、必ずしも遺言書どおりに遺産を相続させることができるわけではありません。すべてを被相続人の遺言書に従ってしまうと、不利益を被る人が出ることがあります。たとえば、妻子がいるにもかかわらず、「他人である知人のAさんに全財産を譲る」というような遺言書を遺した場合です。
このような場合に効力を発揮するのが「遺留分」という考え方です。法定相続人に対しては、法定相続分の最低割合が法律で保障されています(表1の「遺留分」を参照)。もし遺留分を侵害された場合は、そのことを知ったときから1年(かつ相続開始から10年)以内に、遺留分を侵害している人へ減殺(相続額を減らすこと)の請求をすることができます。
なお、相続人以外の親族であっても、亡くなった人に対して無償の介護や看護などの貢献があった場合は、亡くなった人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたと認められ、相続人に対して金銭を請求することができます(特別寄与料/親族が対象で、内縁のパートナーなどは含まれません)。これにより、以前は遺産のことで不利益を被りがちであった長男の妻などにも配慮がなされることになります。
相続の対象となるものは?
相続の対象になるものは、表2のとおりです。これを見ればわかるように、正(プラス)の財産ばかりではなく、借金などの負(マイナス)の財産も相続の対象になります。相続人がマイナスの財産の相続によって不利益を被ると判断した場合は、相続を放棄することもできます。
具体的には、「相続放棄」と「限定承認」があります。「相続放棄」は、プラスの財産も含めてすべての財産の相続を放棄することをいい、相続人ごとに選択できます。一方、「限定承認」は、マイナスの財産をプラスの財産で弁済して、なおプラスの場合のみ相続を承認する意思を表示することをいい、相続人全員の合意が必要です。

相続税はどのくらい?
一定額以上の財産の相続には「相続税」がかかります。相続財産は、必要経費(葬儀費用や埋葬料など)を除いた額が相続税の課税対象となります。ただし、税額の計算にあたって一律に相続財産から差し引くことができる「基礎控除」がありますので、遺産総額が基礎控除額以下なら申告・納税の必要はありません(たとえば、法定相続人が妻と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円/下記②を参照)。相続税額の計算は複雑なので、とりあえず相続税がかかるかどうかを、基礎控除額を目安に考えてみるとよいでしょう。
実際の相続税の計算方法は次のとおりです。基本的には、一人ひとりの相続額を計算し、それに表3の「相続税率」をかけた金額が相続税額ですが、具体的には、概ね次のような方法で計算されます。
①各相続人の正味の課税対象を計算
一人ひとり相続人の相続額(相続開始前3年以内の贈与や死亡退職金も含む)を算出し、埋葬や葬儀などにかかった費用(必要経費)を差し引きます。
②相続人全員の課税対象額を合計
①の各相続人の課税対象額を合計して、そこから基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めます。たとえば、法定相続人が妻と子ども2人(計3人)の場合、基礎控除額は4,800万円となり、相続額の合計がこれに満たない場合には、相続税はかかりません。
③各相続人の課税相続額を計算
②で算出した課税対象額の総額を各人の相続割合(表1の「法定相続割合」)で按分します。この場合、法定相続人がそれぞれの法定相続割合に応じて相続したものとして計算します。たとえば、法定相続人が妻と子ども2人の場合は、妻2分の1、子どもそれぞれにつき4分の1で按分します。
④各相続人の相続税額を計算して合計
③で計算した各相続人の相続税額に相続税率(表3中欄)をかけ、そこから控除額(同右覧)を差し引いて各人の税額を算出します。これを合計したものが、相続税の総額になります。
⑤各人が支払う相続税額を計算
最後に、④で計算した相続税の総額を、(法定相続割合ではなく)財産を取得した人の実際の課税価格で割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します(さらに、配偶者には税額の軽減、未成年や障害者には税額控除があります)。なお、相続人が亡くなった人の配偶者、父母、子どもでない場合は、この金額に20%相当額が加算されます。