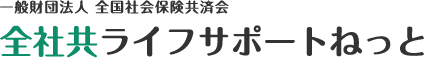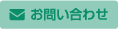要件を満たさず無効になることも
ドラマや映画、小説などでしばしば耳にする「遺言(ゆいごん)」という言葉。死後、遺された家族などに自分の意思を伝え、実行してもらう方法として広く知られていますが、その知識は、あくまでも漠然としたイメージにとどまることが多いのではないでしょうか。
遺言は、法律用語としては「いごん」といいます。法律上の効力があるものを指す時に、専門家が使用し、民法の定める方式に従わなければならないとされています。たとえば、遺言として残せる内容は、相続や財産処分のことなどに限られており、自分の葬儀やお墓に関する希望などは対象になりません。また、自分流のやり方(形式)で死後の意思を残しても、法律上、遺言書として認められず、無効とされてしまいます。
家族に相続問題を残さないようにするためには、法律に従った遺言書をつくることが大切です。
遺言書に必要な形式
遺言書を作成するメリットには、「自分の財産を、誰にどのように残すか」について、自らの意思を明確に示すことで、相続人同士の無用なトラブルを避けられることがあります。また、法定相続人(遺言書がない場合に相続の対象となる人で、配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹など)の範囲を越えて、相続する人を指定することもできます。ただし、遺言として認められるためには、一定の方式に従うことが必要とされています。
民法で定められた遺言の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。(このほかにも、死亡の危急が迫ったときなどに緊急的に作成される「特別の形式」もあります。)

公正証書遺言と秘密証書遺言には、公証人(場合によっては証人も)への費用が発生します。そのため、3つの中で最も安価で手軽なのが自分で作成する「自筆証書遺言」ですが、人の手を借りずに遺言書の内容をまとめ、形式を整える必要があり、十分な知識がない場合にはハードルが高いかもしれません。
また、自分で保管するため、死後、遺言書が発見されないおそれがあり、場合によっては、その内容に反対する相続人によって廃棄されたり、改ざんされたりすることも考えられます。財産の額が大きい場合や、身近にきちんと保管できる環境がない場合は、作成から保管まで専門家が関わる「公正証書遺言」を選択したほうが安心です。
なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管できる制度が始まりました(自筆証書遺言保管制度 ※一定の費用が生じます)。これにより遺言書の紛失や、他人による隠匿・改ざんなどを防ぐことができます。また、保管後、本人が遺言書を閲覧したり、気が変わったら撤回することも可能です。ただし、遺言書を自分で作成しなければならないことに変わりはありません(遺言書保管所は、遺言の内容を審査しません)。作成に不安があるときは、やはり公正証書遺言を選択するといいでしょう。
《コラム》相続は必ずしも遺言書どおりにはならない?遺留分のはなし
相続をすべて被相続人の遺言書に従ってしまうと、不利益を被る人が出ることがあります。たとえば、妻子がいるにもかかわらず、「他人である知人のAさんに全財産を譲る」というような遺言書を残した場合です。このような場合、配偶者、子、父母(祖父母)に対しては、法律で定められた相続分の最低割合が法律で保障されており、請求することができます(たとえば、相続人が子のない配偶者のみの場合、財産の2分の1)。これを「遺留分」といいます。
もし遺留分を侵害された場合は、そのことを知ったときから1年(かつ相続開始から10年)以内に遺留分を侵害している人へ減殺(相続額を減らすこと)の請求をすることができます。
自筆証書遺言の書き方
遺言書はどのように書いたらいいのでしょう。公正証書遺言は公証人に作成を依頼できるので、ここでは、自分で作成する「自筆証書遺言」の書き方を紹介します。
民法では、次のように定められています。なお、筆記用具、用紙、縦書き・横書きなどについて、特に決まりはありません。
◎自筆で作成する
遺言書の全文、日付、氏名を遺言者(本人)が自筆で作成し、押印します。パソコンを使って作成したものは認められません(書き方の例は下図参照)。
◎財産目録の作成
財産に関する内容については、財産目録を添える必要があることも考えられます。この場合、目録はパソコンを使って文書を作成してもかまいません。ただし、記載のある紙面にはすべて署名・押印する必要があります。
◎内容を変更する場合
遺言者(本人)が内容を加えたり除いたりした場合、また、その他の変更を行った場合は、その旨を付記し、署名することが必要です。また、変更した箇所に押印します。

遺言書に残せないことは「エンディングノート」に
遺言書には、形式だけでなく、内容についても制限があることにも注意が必要です。具体的に、遺言として残せるのは、相続に関すること、財産の処分に関すること、身分に関すること(子の認知や、未成年後見人の指定等)などに限られ、死後の希望であれば何でも法的効力をもたせることができるというわけではありません。
でも、病気になって正常な判断能力を失ったときや、からだが思うように動かなくなったときのために、延命治療に関する希望を残しておきたい。また、自分が亡くなったときのために、連絡してほしい人のリストを準備しておかなければ――。このような用途には、「エンディングノート」が最適です。
エンディングノートには遺言書のような法的効力はありませんが、自分に万一のことがあったときに、遺される家族に伝えたい大切なことを書き記しておくことができます。遺言書は自分の死後に開かれるものですが、エンディングノートには、生前の話、たとえば終末期の希望や、生きているうちに家族に伝えたい思いを書き記すことができます。
ただし、ノートの存在を自分だけの秘密にしておくと、いざというときに所在がわからないままになってしまうおそれがあります。むしろ、エンディングノートは家族とのコミュニケーションツールであると考え、その存在を明らかにして、ふだんから話し合っておくことが大切です。